涼しくて長袖を着ました。カレンダーをめくったら即、秋でしたみたいなびっくりな9月1日です。このぶんではバジルに花が咲いてしまうかもしれんと、急いで先端の葉の収穫をしておかねば。
カット前。
カット後。あんまり変わったようにみえませんなあ。
それでも、全4株分集めるとけっこうな分量になってます。バジルソース4人分ぐらいにはなるんじゃなかろうか。
 にほんブログ村 |
 にほんブログ村 |
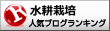 水耕栽培 ブログランキングへ |
涼しくて長袖を着ました。カレンダーをめくったら即、秋でしたみたいなびっくりな9月1日です。このぶんではバジルに花が咲いてしまうかもしれんと、急いで先端の葉の収穫をしておかねば。
カット前。
カット後。あんまり変わったようにみえませんなあ。
それでも、全4株分集めるとけっこうな分量になってます。バジルソース4人分ぐらいにはなるんじゃなかろうか。
 にほんブログ村 |
 にほんブログ村 |
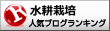 水耕栽培 ブログランキングへ |
朝は汗だく、午後からはひんやり涼しい8月も終わりの日。
5月5日に種まきしたトマトは、花芽どきがちょうど猛暑で実があまりついていません。
おまけに葉が下から枯れくるのでほとんど幹っばかりが目立ちます。
8月27日。まあでも、ちらほら赤い色が(かろうじて)ご覧頂けるのではないでしょうか。
じゃっかんの収穫あり。中玉の「Mr.浅野のけっさく」とミニで黄色いのが「ピッコラカナリア」。
こちらも同じく。
今のところ、中玉の「Mr.浅野のけっさく」が全部で3株と多く、他は2株か1株。浅野さんが希望の希少収穫源なのであります。他のトマトはみな沈黙中。(このまま絶滅?)
8月31日の収穫も、「Mr.浅野のけっさく」のみです。
次なる収穫は、このあたりの枝かしらと物色。
お、しましまのミニトマト(フルーツゼブラ)に変化ありか? ほら、左下のところ!
うっすら赤みが。ん?でも茶色かあ? ううっ、まさか腐ってるんじゃないだろなあ。
ふう。トマトの実は、今や数えるほどしか見あたりません。戦々恐々としておるけふこのごろであります。
 にほんブログ村 |
 にほんブログ村 |
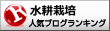 水耕栽培 ブログランキングへ |
ちゃんこネギの種まきは、たしか5月5日だったかと。それがいったいどれぐらい育ったかともうしますとですねえ。こんなですわ。(撮影:8月19日)
あまりに変化なし。この暑さが災いしましたかねえ。
ふと、根元のバーミキュライトに指を突っ込んでみたら、さらっさら。水気ゼロ。
穴鉢を持ち上げてみたら、液体肥料がはいってる水の位置がうーんと底のほうでした。
あんれまです。そりゃあ育ちませんわなあ。いやそれより、よくぞ生きてこられましたことで、でした。
急ぎ液肥の追加。この失敗の原因は、フェルト布を垂らしていなかったことにもよるかと。
いつもならフェルト布を細く裂いたものを数本、黒い穴鉢から垂らしておいて液肥を吸い上げる装置にするんですが。
こんなふうに…(撮影:2020年9月15日)
ところがこのたびはめんどくさくてフェルトの装着をさぼったらこのありさまでして。
いまからでも遅くはない。フェルトつけようかしら。(8/27)
うーん、このままで。「今後は、液肥の観察を怠りなく」の厳重注意ってことですませましょ。へへっ
ともあれ、それぞれの鉢の苗がだいぶ少なくなってしまったので、2鉢を一緒に1鉢にまとめてしまいましょう。
あ~あ、それにしても、長く垂れたままの葉っぱが哀れなるべし。そのうちピンって直立してくれるかなあ。
 にほんブログ村 |
 にほんブログ村 |
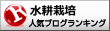 水耕栽培 ブログランキングへ |
5月5日に種まきしたルッコラです。葉っぱが黄色になってます。
こんなのがちらほら。虫でもいるかと探してみるも、みつからず。うーむ、暑さが続いてますし、そろそろお疲れですかねえ。
2日後(8/25)。おっ、水切かごの底が隠れてきたんでないかい?
お早い成長っぷりですな。その調子でひとつよろしく!
【おまけ:夏の風物詩/ホヤ】
スーパーでホヤを売ってました。1個138円也。夏が旬のホヤ。もうこれが最後になるかも。きょうのは身がぷりっぷりに入ってる。どうです?おひとつ。
…と、ホヤに言われたような気がして、買ってしまったおふたつも。
開封のしかたですが、おへそのようなでっぱりを1個につき2カ所切り落とします。すると内容物が皮に接着している面がなくなるので、あとは皮だけをハサミで切れば中身がするりと登場。水分いっぱいのふっくらした身ですなあ。
えーっ、私、べつに好きじゃないからいいです~、っていわれそう。
変な食べ物だなあとは思います、私も。
海育ちなもので、ホヤは季節もんのトウモロコシとかみたいな通常食品として取り扱う感覚なのです。
実家の母に電話で「ホヤ1個138円で買って食べた」と申しましたら、「なんてお高い!」と絶句してました。「ホヤなんて、買うもんじゃなくてご近所さんからもらって食べるもんだ」と思ってるからでしょう。
それにしても、近頃、近所のスーパーさんでちょくちょくみかけるホヤ。そうそう好まれる食品とは思えんのだが、いったいどなたかお買い求めなのだろう?
物陰にかくれて、こっそり確かめてみたいもんであります。
 にほんブログ村 |
 にほんブログ村 |
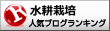 水耕栽培 ブログランキングへ |
栗を頂戴しました。近所でお借りしている畑で先日拾ったのと同じ木のものです。前回は手のひらにのる量だったので調理は短時間ですみましたが、こたびはこんなに。
どうやったら楽に手早く皮むきができるか。これが問題であります。
とりあえずネット検索してクラシルというサイトさんの「圧力鍋で時短 栗の茹で方 レシピ・作り方」をまねて圧力鍋で茹でることに。
さらに項目を付け加え、「皮にいれる切れ目のつけかた」を2種類にわけて実験してみることにしました。なお、栗はあらかじめ一晩水に浸け、皮を少し柔らかくしておきました。
これはその後です。
【皮のむき方:てっぺんむき】クラシルでは、クリのとがったところに包丁で1カ所切れ目を入れていたのですが、今回は十文字に入れることにします。なお、切れ目はハサミを使ってみたらこわくなくて簡単でした。
その際、まず、厚みの少ないほうに1回目の切れ目を入れます。
その後、あけた穴にハサミを差し込んで十文字になるように追加の切れ目を入れました。
 にほんブログ村 |
 にほんブログ村 |
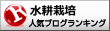 水耕栽培 ブログランキングへ |