ルッコラの種まきをしたのが7月22日。7日たちました。双葉がでたあと、茎がびろ~んと背伸びしてます。いかんいかん。
倒れちゃいかんので、バーミキュライトを追加。しかし背丈がまちまちだからどこまで入れていいもんだかわからん。しかも、葉にバーミキュライトの粒がついてしまったので霧吹きで水をかけてみたけど、うまく落ちてくれません。ん、もう、ややこしい。
せっかくだから、外側の水切りザルと桶も洗っておこう。ついでに、今までは底面に水を入れていたけど、液体肥料(ハイポニカ液肥)にとりかえてみるか。このタイミングで切り替えていいのかわからんけど。本葉を出すには栄養がいりそうな気がするもの。
一方、こちら先発で5月5日に種まきしたルッコラです。
ほっておくと葉が横に倒れて折れたりするので、なるべく早めに収穫したほうがよさそうです。というのも、日向で育てると葉が固くて食感がよろしくないので半日陰に設置してるのでやや弱々しく(柔らかく?)なってしまうのが原因かと。痛し痒しですわ。
このひとつかみは、サラダにいれますか。
ついでに、シソも。どさっ!
昨日もフェンスに設置したプラ容器のをとったけど、今日のはコンテナ植えから刈り取りました。こちらは、ハマキムシにやられてだいぶ穴だらけになっとります。
それにしても、シソばっかりこんなに育ててどーすんだですが。なにしろ珍しく発芽がよろしかったもんですから、もったいなくて全部育てたらこうなっちゃいました。
もうね、当分、シソとルッコラ、バジルが主役の献立でまいろうかと。で、昨日と今日は「焼き肉」。その次は「なま春巻き」はどうでしょう。
だが、そのあとが思いつかない…
とぼしい調理力には自信がありまーす。へへっ
 にほんブログ村 |
 にほんブログ村 |
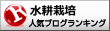 水耕栽培 ブログランキングへ |















































