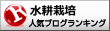先日、近所で二人の友人たちとお借りしている畑でジャガイモを掘りました。小さなお子さんも一緒で、賑やか。こういう収穫は大勢なほうが楽しいとあらためて思ったことでした。
さて、ジャガイモ。
どこにどう保存しておきますかねえ。ここはマンション、狭き部屋。ガスメーターやちょっとした物置もあるけど、屋外に接しているためか夏は温度が上がるんです。となると、北側に位置する玄関だろうか。ドアを隔てているためかわりに涼しく、出入りするところだから風通しもそこそこありそうだ。
だが、このビニール袋に入ったまま靴箱の横に置いておくというのもねえ。ふんずけそうじゃないか。
そこで考えましたぞ。とりいだしたる新聞紙。ユーチュウブさんのご指導のもと出来上がったのがこちらの3個。
新聞紙で作る紙袋。本体は新聞3枚の厚さできており、持ち手はあとからとりつけています。製作時間は1個10分くらいだろうか。ボンドで貼りつつ折る。手がインクで真っ黒になりましたが洗えばよし。
この3個に、キタアカリ、ダンシャク、メークイン、の3種類をそれぞれ分け入れた。
キタアカリが一番多いぞ。あ、そういえば、これより前にすでにマンションのお隣さんに合計15個おすそ分けしたけど、3種類5個ずつだから、どれもおなじだけ少なくなってるわけで。ほう、キタアカリって収量が多い品種なんですかねえ。
紙袋は持ち上げても大丈夫、ではありませんでした。1本だけ紐が抜けましたね。たぶん接着面積が少ないせいだと思います。もっと太くて広い持ち手にしたらよかったなあ。
ま、ともあれこれで通気性はよし。あ、遮光もしなくちゃね。ということで、上に新聞紙をのっけました。わーい簡単。これでどうじゃろか?
ジャガイモの保存には段ボールもよさそうだけど、ちょうどリサイクルに出したばっかりだし。紙袋も適当なのがなかったし。じつは新聞紙だってなかったのだ。新聞はネット配信を購読しているので「紙」のはとっていないのです。それがたまたま新聞紙をいただくことがあったのでようやくこんな紙袋を作れたというわけです。
それにしても、新聞「紙」がないとけっこう不便だなあとは思いますな、こんなとき。うちにはしたがって広告紙もないわけで、ちょっとした汚れ物処理に使う紙がない。
でもまあなんとかなるもんで、毎月2回発行される市の広報誌がその代わりを補ってくれてます。いい紙でできてましてね、水にもわりに強いんですよこれ。魚をさばくときの下敷きになり、取り出した贓物と一緒に丸めてゴミ箱へポイ。いい仕事してくれます、青梅市の広報誌。
それもなくなってしまったら、しかたがない、コンビニに走るのさ、新聞「紙」買いに。
(なお、上の写真の魚はイナダ。近所のスーパー出身で一尾600円也。)