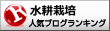涼しくて秋風も吹こうかという朝(21度)から、一気に汗だくの夏・真昼(32度)に変化するもんだとは。いやはや、ぐったりな日であります。
昨日(8/18)、だいだい色の「ピッコラカナリア」に割れた実発見。
プチッとはずして半分に割ってみました。外側の果肉やや厚め。種まわりに果汁あり。
これ、おいしいんだろか? 今期、お初の試食です。
食べた瞬間、「ニンジン!」。ほんわかと甘味ですっぱさ薄め。ニンジン色だし。
種のサイトさんによれば、ピッコラカナリアは「橙色ミニトマト、高糖度(Brix9~11%)、濃厚でとろける食感。一般のオレンジ種よりもベータカロテンを2.5倍も多く含有(女子栄養大学調べ)」だそうです。
ふむふむ、「ベータカロテン」というのはニンジンの味がするものかどうかは知りませんが、ジューシーなニンジン風味でしたなあ。
なお、「濃厚でとろける食感」という表示は見なかったことにします。あしからず。
本日(8/19)。昨日収穫した2段目の残りも、割れちゃう前にとってみようと思います。
さらに、その下の1段目のもいってみよう。2段目がまずまずOKなんだもの、もういけるんじゃないかと。
一緒に、中玉の「Mr.浅野のけっさく」も収穫。あ、小粒でも赤いのは浅野さんです。
きょうのピッコラカナリアは、昨日とちがってすっぱくて、「おっ、ちゃんと普通にトマトじゃん」でした。なお、皮固めなので、よおくカミカミするお楽しみつきです。
収穫するのがちょっと早かったのかもしれません。
ところで、ピッコラカナリアは、「ソバージュ栽培」(脇芽はとらずにおおむね放任で育てていく)とやらの栽培方法も適用できるんだそうで。ただし、サンマルツアーノやシシリアンルージュ、ロッソナポリタンをソバージュ栽培するよりは収量が落ちるそうですが。
当ベランダは極小ですから、そんな楽しげな自由放任はとても望めませんが、ちょっと憧れますわねえ。すこしならやってみたいなあと思わんでも。
ああそれなのに、先日、先端の枝を切ってしまいました。だって細くて弱々しくて花芽がすべて落ちてしまうので役に立たないんだものバッサリやるしかないでしょうよ。まだたったの3段目までしかできてませんでしたがね。
ま、でも、根元に生えてきた脇芽は残しておりましたので、これでなんとか。
今、実がついている幹の収穫が終わる頃(といっても残り8粒ぽっち)、この根元の脇芽を主体に切り替え(最初の幹はバッサリ切り落として)、第2期ピッコラカナリア時代を樹立していただきたいと思っておるしだいです。
しかしこの暑さですからねえ、またしても短命になりそうな…